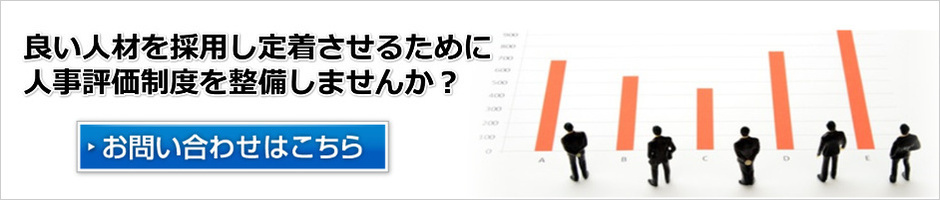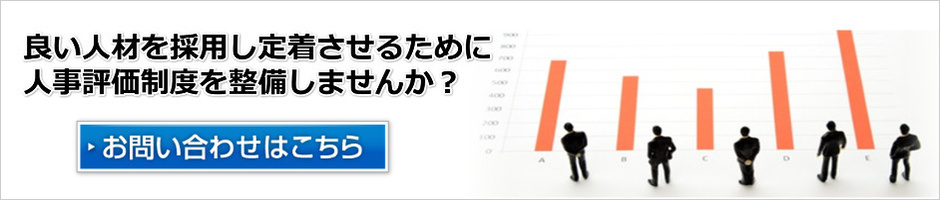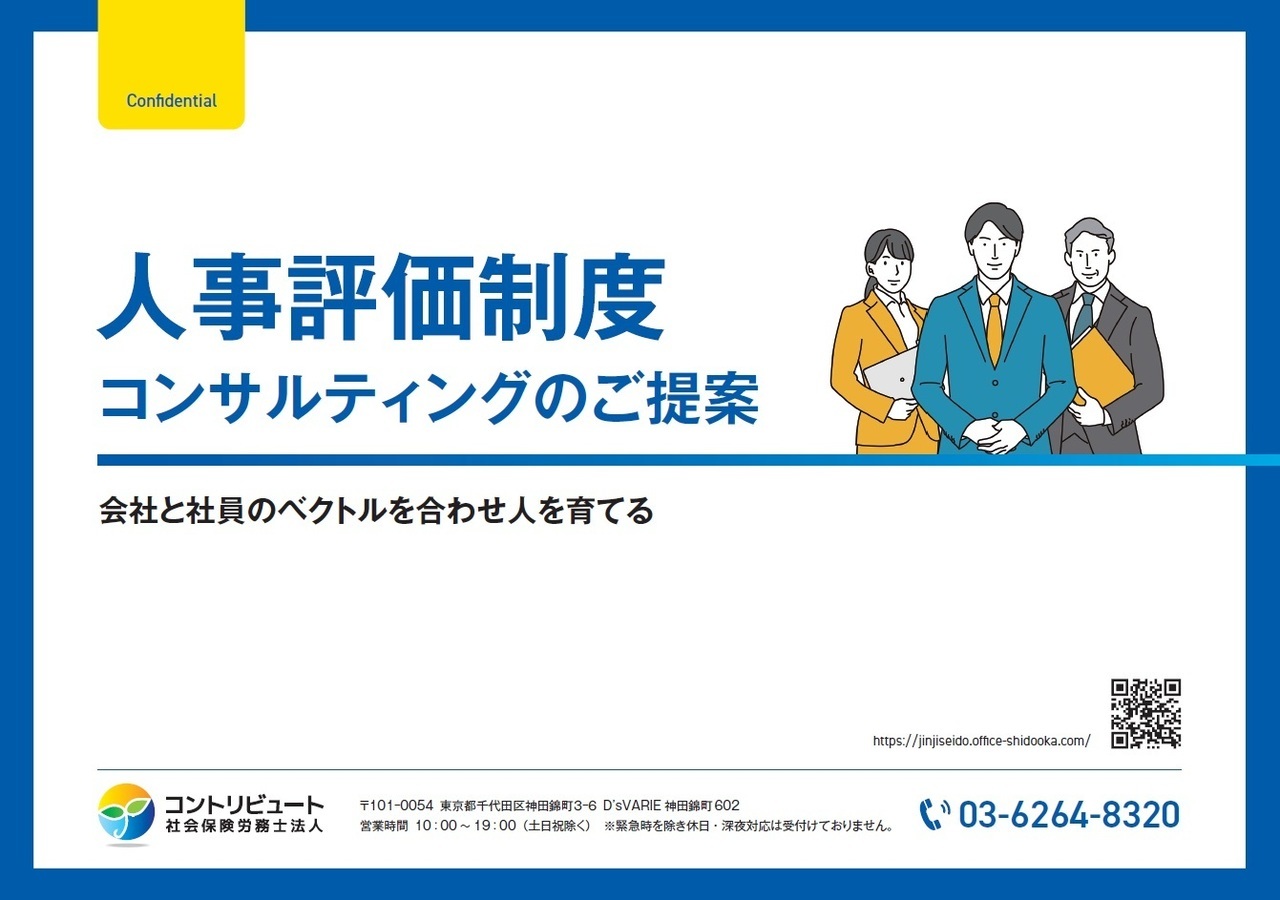〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-6 D'sVARIE神田錦町602
営業時間 | 10:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
降給の理由と対策を徹底解説|就業規則と法律の観点から専門家がアドバイス
貢献度と賃金のギャップが生じている会社
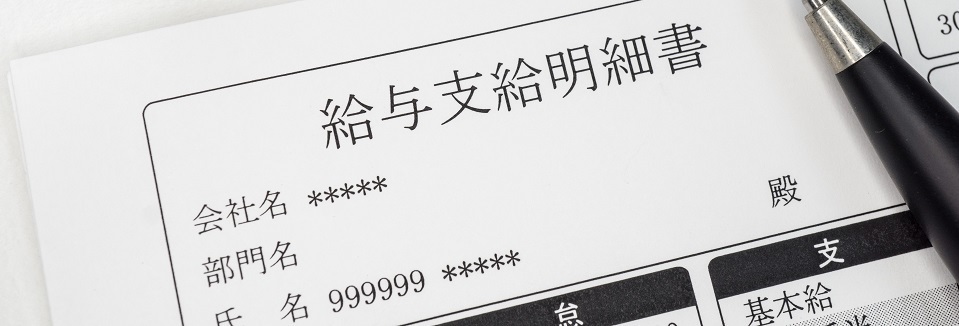
- 人事制度の中に降格や降給の制度を取り入れたいがどのようにすればいいかわからない。
- 降格や降給は会社が一方的にできるものなのか?(対象者の同意がなくても実行できるのか)
- 降格や降給を実施する場合の注意点は?
- 人事制度の中に降格や降給を入れなければ降給することはできないのか?
自社の人事制度や賃金制度について、このようなお悩みはありませんか?
通常、賃金・給与は会社への貢献度によって、その貢献度が高まれば、比例して給与額も上がっていくようになっています。
悩ましいのは、中小企業では特にこの貢献度の図り方が曖昧なこともあり、いつの間にか貢献度と給与額にギャップを生じることにあります。
例えば、ギャップを生じるパターンとしては、次のようなケースが考えられます。
(ケース1)
- 老舗の企業で、従来から勤続年数や年齢により給与が高る仕組みになっており、能力評価や人事評価を行って来なかった。
- 経営者の世代交代などで人事制度を導入した際、社歴の長い古参社員の給与が非常に高止まり状態になってしまっているケース。
(ケース2)
- いままでは経営者の好き嫌いと頭の中での感覚で昇給を決めており、上司に気に入られれば給与があがっていた。
- ところが、時代の変化に伴い、M&Aにより経営者が交代した際、給与と職責、成果が結びつかない社員がでてしまっているケース。
日本の労使慣行では、給与、特に月給は一度上がったら「下がらない」という考えがあります。
法律の考えや解釈としても、労働条件を下げる場合には、原則として労働者の同意が必要とされており、給与を「下げる」ことにはかなり大きな制限がかかるというのが実態です。
そうはいっても、競争環境の厳しい今の時代、経営者としては、貢献度と給与額にギャップが生じている場合は、そのギャップを是正する対応を打ちたいと考えるのが自然です。
賃金が下がる降格・降給のパターン
ではここで、給与が下がるというケースを考えてみます。
一口に賃金が下がる降給といっても、様々なパターンがあります。
まずはそのパターンを分類してみると、以下のような分類となります。
- 懲戒処分により減給処分となるケース
- 懲戒処分として降格となりその結果、役職手当などの支給がなくなることで減給となるケース
- 人事制度上の評価により降格・降給となるケースにより減給となるケース
- 労使双方の合意に基づき、労働条件の変更により給与を変更させるケース
- 就業規則の変更により給与が下がるケース
上記のように様々なパターンがあります。
この5つの中で、1の減給処分のみ、一時的に給与が減額される措置となり、他のパターンでは原則一時的ではない恒久的な降給措置となります。
賃金を下げることができる仕組みは必要?
既に述べた通り、従来の年功序列型賃金を主流とした日本の会社ではあまり給与を下げる、という考え、思想で賃金制度が設計されていません。
一部例外的に、年齢給がある一定の年齢になると下がるといったことや、定年後の再雇用のタイミングで給与が下がるということはありますが、あくまで例外です。
基本的には勤務年数が長くなれば、給与は上がり続けるというのが日本の会社での給与への考え方です。
本記事を読まれている方の会社でも、毎年給与がアップダウンする、というような企業はほとんどないでしょう。
降格や降給は基本的には行われず、人事評価が悪い場合であっても、「現状維持」が多いでしょう。
しかし、高度経済成長期のような、商品やサービスを作れば売れるという時代ではありません。
勤続年数が長くなれば、会社業績への貢献度が比例して継続して高くなるかといえば、わからなくなってきています。
経営者としても、事業環境が変化した際に、会社への業績・貢献度と給与とのギャップを少しでも是正できる仕組みを整えることは意味があります。
降格・降給のある人事評価制度を導入したい
前提条件として、今まで人事評価の結果で賃金を下げることがなかった会社や、新しく人事評価制度を導入する会社では、賃金が下がる可能性がある人事評価制度を導入する際に、就業規則の不利益変更の問題をクリアする必要があります。
これは、人事評価の結果として、賃金の減額が発生する可能性がある制度への変更を行う場合、人事評価の結果、労働者の不利益になる可能性があれば不利益変更に該当するものと判断されるためです。
ここで、就業規則の不利益変更を行う場合には、労働者からの同意または就業規則変更の合理性が必要となります。
同意が得られれば特に問題はありませんが、社員数の多い会社になると、一部の社員のみが反対するといった状況が発生し、社員全員から同意を得るのが難しくなることも生じます。
この場合は、賃金が下がる制度の導入であっても、その制度の内容が適切に「周知」され、「合理的なものである」場合は、社員との合意がなくとも行うことができるとされています。これが、同意に変わる就業規則変更の合理性となります。
この合理性の判断はグレーゾーンになるため、判断が難しい部分ではありますが、ポイントとしては、以下のような点で合理的な変更かどうかが判断されます。
1)労働者の受ける不利益の程度
2)労働条件の変更の必要性
3)変更後の就業規則の内容の相当性
4)労働組合等との交渉の状況
5)その他の就業規則の変更に係る事情
まとめると、あまり激しい下げ幅、要件にせず(不利益の程度を弱める)、社員にきちんと制度変更の趣旨や意味を説明したうえで制度を導入する、となります。
なお、降給とする場合の額やパーセントについては、もちろん小さければ小さいほど不利益の程度は小さく、その分合理性の根拠となりますが、何パーセントまでならいいという明確な基準はありません。
人事評価制度の降格・降給の判断ポイント
人事評価の結果として降格・降給をする場合、降格は社員の同意を得ることなく、会社の判断で行う行為になります。
このような降格を一方的に実施してよいか?という点については、認められる場合もあれば認められない場合もある。つまり、判断が分かれるグレーゾーンとなります。
ポイントとしては、上記の賃金減額の可能性がある制度を導入する際の要件がクリアできているとすれば、今度は、制度を運用するうえで「人事評価制度が公平かつ適切に運用されているか」が問われます。
これは例えば、以下のような場合に人事制度自体が公正性・客観性が乏しく、裁量権・人事権を濫用しているとして降格や降給が違法となる可能性があります。
〇人事評価の、評価基準が抽象的な定めとなっており、評価者の恣意的な運用が為される
〇人事評価の手続きが不明確、不透明で社員にオープンにされていない
〇評価基準がそもそもオープンにされていない
上記のようなリスクがあるため、会社としては、人事評価の評価基準や評価の手続きといった制度の内容を明確にし、社員にオープンにすることが重要となります。
年俸制の改定を行う場合
うちの会社は年俸制だから、毎年洗い替えができるはずだよ!
最近では外資系企業やITベンチャーなどを中心に年俸制を導入する企業も増えてきていますが、年俸制の場合は給与の減額改定が行いやすいといったことはあるのでしょうか?
答えはNO。
年俸制だからといって、会社側が一方的に給与(年俸)を下げることはできません。
確かに、年俸の交渉をすることはできますが、労働者側が拒否をすれば、一方的に給与の切り下げ、労働条件の不利益変更ができるわけではありません。
原則としては、給与を下げる場合には、労働者の同意が必要になります。
このあたりは、年俸制だろうが、月給制だろうが同じです。
一方で、上記にも記載の通り、人事評価の結果として給与テーブルでどの程度の上げ下げがあるかを明確にし、適切に人事評価制度を運用することができれば、月給制と同じように年俸制であっても、制度の仕組みとして降給を行うことが認められるケースもあります。
(これは上記で述べた通りグレーゾーンとなります)
最も大事なのは評価の納得性
さて、ここまで人事評価制度における降格・降給についてご説明しましたが、結局のところ、最も重要な点は評価結果に対する社員の納得感です。
上司からフィードバックされた評価結果に社員が納得していれば、その結果も受けいれることができます。
人事評価を受け入れることができるということは、給与の改定にも納得するということにも繋がり、同意をもって給与改定を行うことへ進めることも可能になります。
法的な基準があいまい、グレーゾーンであるからこそ、人事評価制度ではこの「納得感」が最も重要となります。
弊社のコンピテンシー型人事評価制度は、求める要件や求めるレベルを会社ごとにオリジナルに作成することができ、なおかつ評価基準を客観的に明確にすることができます。
社員の人事評価の納得感を高めたい!というご要望がある企業様のご相談をお待ちしております。
月給での降給よりも、賞与での査定方法をまずは見直すことも一つの案
人事評価を行って月給を上げる、下げるということとは別に、その人事評価をもとにまずは賞与の金額に反映する、ということも考えられます。
従来の日本企業の賞与は、古い会社では月給の*ヶ月分、基本給の*ヶ月分支給する、といった基本給連動、月給連動の賞与を支給する会社が主流でした。
この基本給連動方式の良い点は、賞与の都度査定を行う必要がなく、また、全体での計算や賞与原資とからの算出がしやすい、わかりやすいといったメリットがあります。
一方で、その期の成果、パフォーマンスがどの程度個々人に反映されているのかわかりにくいといったことや、年功型の賃金制度では社歴の長い人ほど成果がなくとも賞与も多くなるといったデメリットもあります。
さすがに最近は、賃金制度で、賞与は夏冬基本給の*ヶ月分支給する、といった規定をみることも減ってきましたが、規定では書いていなくとも、経営者の頭の中の計算として基本給の*ヶ月分支給する、という考え方は根強く残っているように感じます。
人事評価制度を導入した結果、どのように賃金にリンクさせるのかという点は非常に大きな課題になりますが、月給をいきなり上げ下げするよりは、まずは賞与に人事評価制度の結果を反映させる、というやり方もあります。
一つの考えとして頭に入れておいて頂ければ幸いです。
【補足】日本では本当の意味でのジョブ型賃金が導入できない理由
ここで、1つ補足の案内として近年話題のジョブ型雇用についてご紹介したいと思います。
弊社での考えになりますが、日本の労働関係法令と本来のジョブ型雇用は相性が悪すぎて
導入することが厳しいです。正直に言って今のままでは無理です。
では、なぜジョブ型雇用を導入することができないか?
次の2つがネックになります。
〇解雇規制が厳しすぎること
〇賃金を簡単に下げられないこと
ジョブ型雇用では、ジョブ(仕事)の内容ごとに仕事の要件と報酬を定義します。
ここで問題は、ジョブが変わるときです。
本来のジョブ型雇用というのは、そのジョブ(仕事)がなくなれば解雇して他の会社へ行ってください、というのがOKとなります。
しかし、現在の日本の労働法では解雇の規制は非常に厳しく、そんなに簡単に解雇をすることはできません。
例えば、事業内容や事業方針の転換で会社に必要な職種や業務が、採用時想定していたジョブからがらりと変わったとします。
欧米の場合は、
「会社の方針が変わったので、従来の仕事はやらなくなりました。残念ですがあなたの仕事はなくなってしまいました。つきましては、他の会社へ行って下さい」と解雇となります。
もしくは、「新しい方針ではこのジョブになります。このジョブの要件は〇〇、求められる成果は**で、対応する賃金は△△となります。」と新しいジョブに応じた報酬に変更されます。
ところが日本の場合は、事業環境の変化や事業方針の変更があったとしても解雇ができず、人事異動・配置転換で「雇用を守る」ことが求められます。
さらに、人事異動・配置転換し、その配転先のスキルや経験がゼロだったとしても、そう簡単に賃金をそのジョブに応じた額に下げることができません。
簡単にいってしまえば、全ての労働者に適用される「労働基準法」の思想自体が欧米のいう「ジョブ型」ではなく、「メンバーシップ型」となっています。
これは、別にどちらが良い・悪い、というものではなく、国民性や文化、考え方の違いによるところが大きいと考えています。
そのため、少なくとも、ジョブを変えることで「賃金を下げることは可能になる」という工夫を法令でしなければ、なかなか本来の意味でのジョブ型雇用は実現できないだろう、と弊社では考えております。
ジョブ型雇用とは、雇用といっていますが、イメージとしては、全員が業務委託になると考えればしっくりきます。
外注業者に、ある業務(ジョブ)を定義して契約して報酬を支払います。
では皆さん、事業環境の変化でその業務が不要になって新しいジョブが必要になった場合、どうしますか?
不要となったジョブの外注業者は契約を終了し、必要になったジョブの外注業者と契約しますよね?
これが雇用の場でもできるかといえば、現状は、できません。
そんなわけで、巷で騒がれている、職務記述書(ジョブディスクリプション)を一生懸命作成しても、ジョブ型雇用は上記の理由で実現するのは厳しいです。
また、集団として和を保ち、一致団結して成果を出す日本の国民性に果たしてジョブ型賃金が合うのかどうかも疑わしいところがあります。
会社のカルチャーにフィットする人をメンバーとして迎え入れ、事業環境が変わったら、自分のジョブも変わって会社が求めることを一生懸命実行する。
その代わりに賃金は保証する、というメンバーシップ型はそんなに悪いやり方でもなく、むしろ日本人には合っているような気もします。
これから労働法制がどのように変わるかによりますが、今までの流れから、「労働者保護」が弱まるとはあまり思えません。
一時期、成果主義がでてきた時と同じように、今回も本来のジョブ型雇用とは違う「なんちゃってジョブ型雇用」を導入し、うまくいかずに元に戻るような気もします。
専門家の社労士に相談して自社に合った賃金制度への見直しをしませんか?
さて、ここまでいろんな面から、人事評価と賃金を下げる、ということについてご紹介してきました。
下げる仕組みがあった方がいいのかどうかは会社によって異なりますし、合う合わないがあります。
賃金の問題は経営者、人事部門が一番頭を悩ます問題でもあります。
専門家の社労士と一緒に、あなたの会社にあう賃金制度、人事評価制度を検討してみませんか?
人事評価制度のお問い合わせはこちら
東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当法人では中小企業の人事評価制度作成、改定、運用のサポートを実施しております。
※ZOOMでのオンラインミーティングも対応可能です。
■東京都千代田区神田錦町3-6 D'sVARIE神田錦町602
■受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)