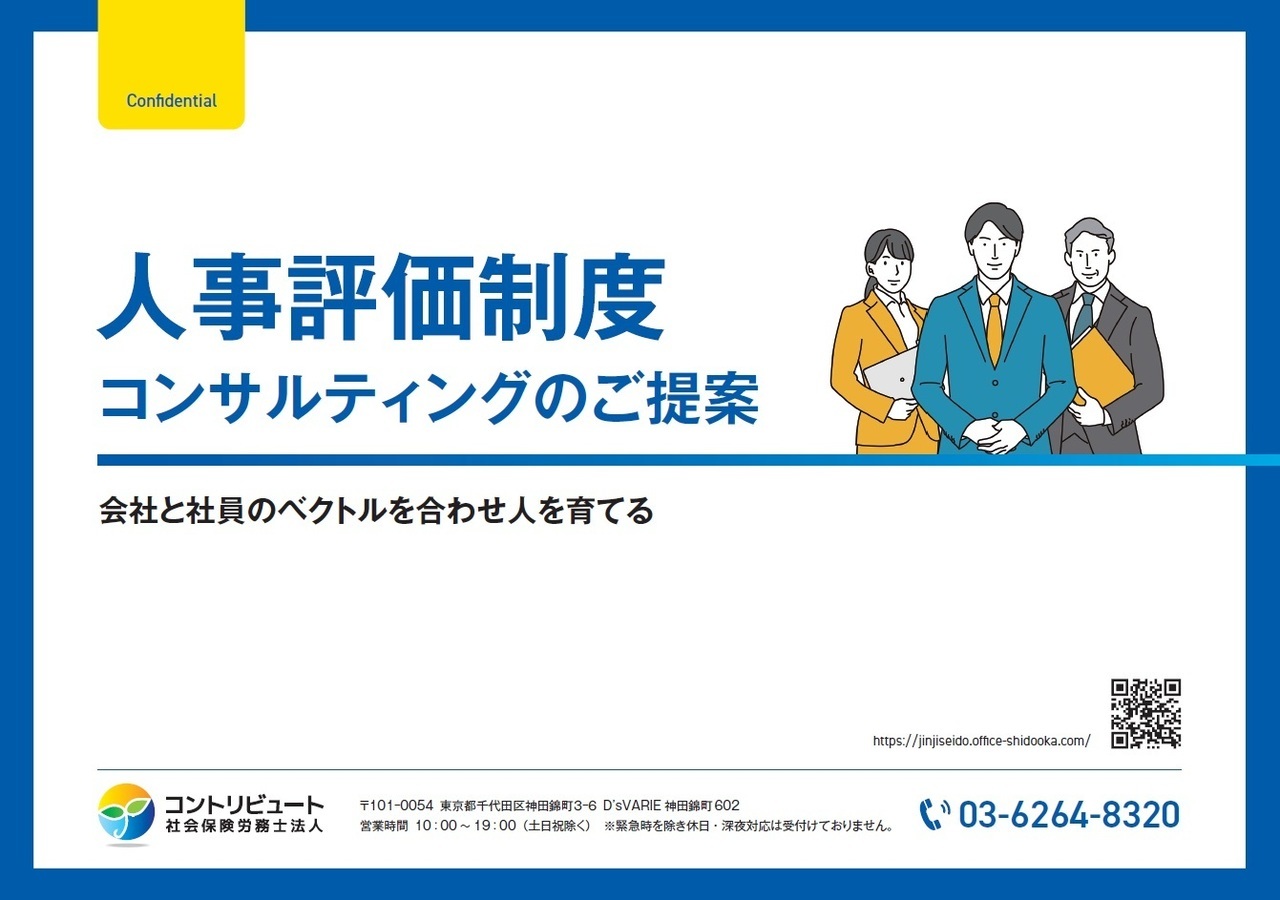〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-6 D'sVARIE神田錦町602
営業時間 | 10:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
人事評価規程のポイントとサンプル公開|社労士が解説
人事評価はそもそも経営側の専権事項

経営者(会社側)の権利の1つに「人事権」があります。
社員の人事評価を行うことは、この人事権に含まれます。
そのため、本来人事評価について、経営者(会社側)がどのように実施するかは、経営者(会社側)に大幅な裁量権が認められています。
- どのような能力を、会社において重要なものと評価するか?
- どの程度のことができていたら良い評価とするか?普通の評価とするか?
- 人事評価の結果、どのような処遇にするか?
これらは、経営者(会社側)の匙加減でもあります。
しかし、だからこそ、人事評価は経営者の好き嫌いによって決まる、公平ではない、評価基準が曖昧といった社員にとっての不満につながっているという実態があります。
このページをご覧頂いている方も、そういった現状を理解しているからこそ、「人事評価の仕組みや評価の基準は社員にオープンにするべきだ」という考えを持たれていると思います。
人事評価規程は会社に必須なのか?
人事評価規程は就業規則における「相対的必要記載事項」と位置付けられています。
規程を定めるかどうかについては会社の自由です。しかし、ルールを定めた場合には必ず記載しなければならない事項となります。
そのため、明確なルールになっていないのであれば、人事評価規程は作成する必要はありません。
簡単にいえば、社内に制度として人事評価の仕組みがないのであれば、当然ながら人事評価規程は必要ありません。
社員の不満を解消するために、「人事評価のルールを明確にする」という目的がある以上、作成したルールを人事評価規程として明文化し、社員にオープンにする必要があるのは前提条件となります。
人事評価のルールを経営者が考えた。でも、オープンにはしない。自分だけ(もしくは取締役のみ)が知っている。評価基準も社員には知らせない。
このような状況では、社員の不満を解消し、社員を成長させる仕組みとして人事評価制度を作成する意味がそもそもなくなってしまいます。
社内の制度として人事評価制度を作った場合には、その制度の内容を人事評価制度に定める必要があります。
人事評価制度設計上の就業規則の注意点
人事評価制度を設計またはリニューアルし、就業規則や賃金規程、人事評価規程を作成する際の一番の注意点は就業規則の不利益変更です。
人事評価制度を検討していくと、現在の労働条件よりも、待遇が悪化する(可能性のある)制度を導入することが起こります。
例えば、今までは人事評価がなかった会社に、人事評価制度を新たに導入し毎年の人事評価の結果、賃金が下がる可能性のある制度を導入するようなケースです。
このようなケースは、就業規則の不利益変更に該当することが考えられ、安易に会社側が一方的に変更することができなくなります。
人事評価規程を作成する場合にルール化しておくべき内容
人事評価に関するルールを明文化しよう!と思った場合は人事評価規程を作成することになりますが、人事評価規程を作成する場合には、以下のような項目についてルールを定めておくといいでしょう。
- 人事評価の評価要素、評価項目
- 人事評価の実施方法
- 人事評価の実施者
- 人事評価の時期、査定対象期間
- 人事評価の対象者、適用範囲
人事評価規程のサンプルをご紹介
それでは実際の人事評価規程のサンプルをご紹介いたします。評価方法や評価の時期、評価結果の反映などについて明確にしておきます。
また、多くの場合、一番重要な評価要素や評価基準については別途作成する評価基準書により行うことになります。
人事評価規程のサンプル
人事評価規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 株式会社〇〇〇〇の人事評価は、この規程の定めるところにより行う。
2 人事評価は、社員の一定期間の業務成績及び職務能力、会社への貢献度、目標達成度などを総合的に評価し、これに基づいて賃金改定等を行うことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 人事評価の対象者は、原則として全社員とするが、評価の対象となる勤務期間が6ヶ月に満たない者など会社が人事評価をするタイミングではないと判断したものについては人事評価を実施しないものとする。
第2章 人事評価の方法・時期・評価方法等
(人事評価の時期)
第3条 人事評価は、原則として毎年1回〇月に実施する。ただし、業務の都合上、前後する月で実施することができるものとする。
2 評価の査定期間、及び各評価の査定結果の反映項目は、以下の通りとする。
人事評価時期 査定期間 査定結果反映
*月 *月~*月 決算賞与及び賃金改定
(評価方法および評価方法)
第4条 人事評価は、被評価者ごとに、別に定める評価基準書にて実施する。
2 評価基準書の評価項目や評価基準に関する内容は、必要に応じ適宜変更することができるものとする。
第3章 評価の実施・賃金改定
(評価者)
第5条 評価のプロセスは、以下の通りとする。
(1)被評価者がまずは自身で自己評価を行う。
(2)被評価者を指導監督する立場にある者が最終決定評価を行う。
(賃金改定)
第6条 人事評価に基づく賃金改定は、原則として毎年1回、*月分より改定を実施する。
付 則
この規程は、****年*月*日から実施する。
人事評価規程の作成は誰に頼むのがいいか?
人事評価制度を作成、改定した場合はその内容を就業規則、賃金規程、人事評価規程に落とし込む必要があります。
この作業は、就業規則や賃金規程の改定といった「就業規則の変更」業務となります。
就業規則の変更業務が最も得意な人は、社会保険労務士となります。
人事コンサルタントや人事コンサル会社と社会保険労務士や社会保険労務士法人との違いはこの就業規則の整備の部分にあるといってもいいでしょう。
制度の設計や運用は人事コンサルタントに依頼したとしても、就業規則の変更や整備は社会保険労務士が日常的に実施しており、経験も豊富です。
人事コンサル会社によっては、コンサル会社と提携している社会保険労務士を紹介してくれるケースもあるでしょう。
サービス範囲の中に「就業規則の変更業務」が含まれるかといった点も、人事評価制度を依頼する際のポイントとなります。
なお、就業規則についてもっと知りたい方は以下のページにて詳しくポイントを解説しています。合わせてご案内いたします。
人事評価規程を作成した場合は、社内への周知を実施する
人事評価制度を作成した場合は、その内容を就業規則の一部となります。
そのため、内容を社員に周知する必要があります。
なお、就業規則の周知についてさらに詳しく知りたい方は以下のページにてポイントを解説しています。合わせてご案内いたします。
人事評価規程を作成した場合は、労働基準監督署への届出も行う
最後に、人事評価制度の作成や改定をした場合に必要な手続きについてです。
既にご案内の通り、人事評価規程は就業規則の一部となりますので、作成や改定を行った場合は労働基準監督署に届出を行う必要があります。
就業規則の届出については以下のページにてポイントを解説しています。合わせてご案内いたします。
人事評価制度のお問い合わせはこちら
東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当法人では中小企業の人事評価制度作成、改定、運用のサポートを実施しております。
※ZOOMでのオンラインミーティングも対応可能です。
■東京都千代田区神田錦町3-6 D'sVARIE神田錦町602
■受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)