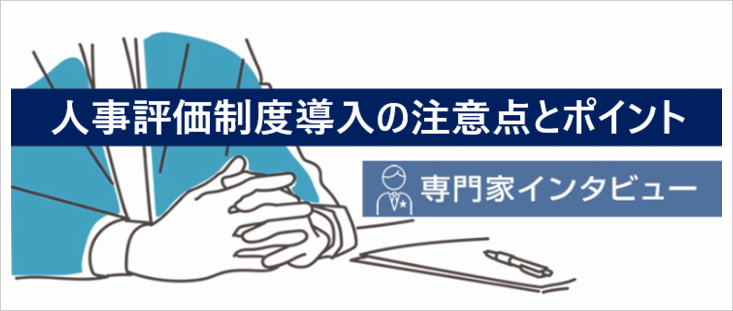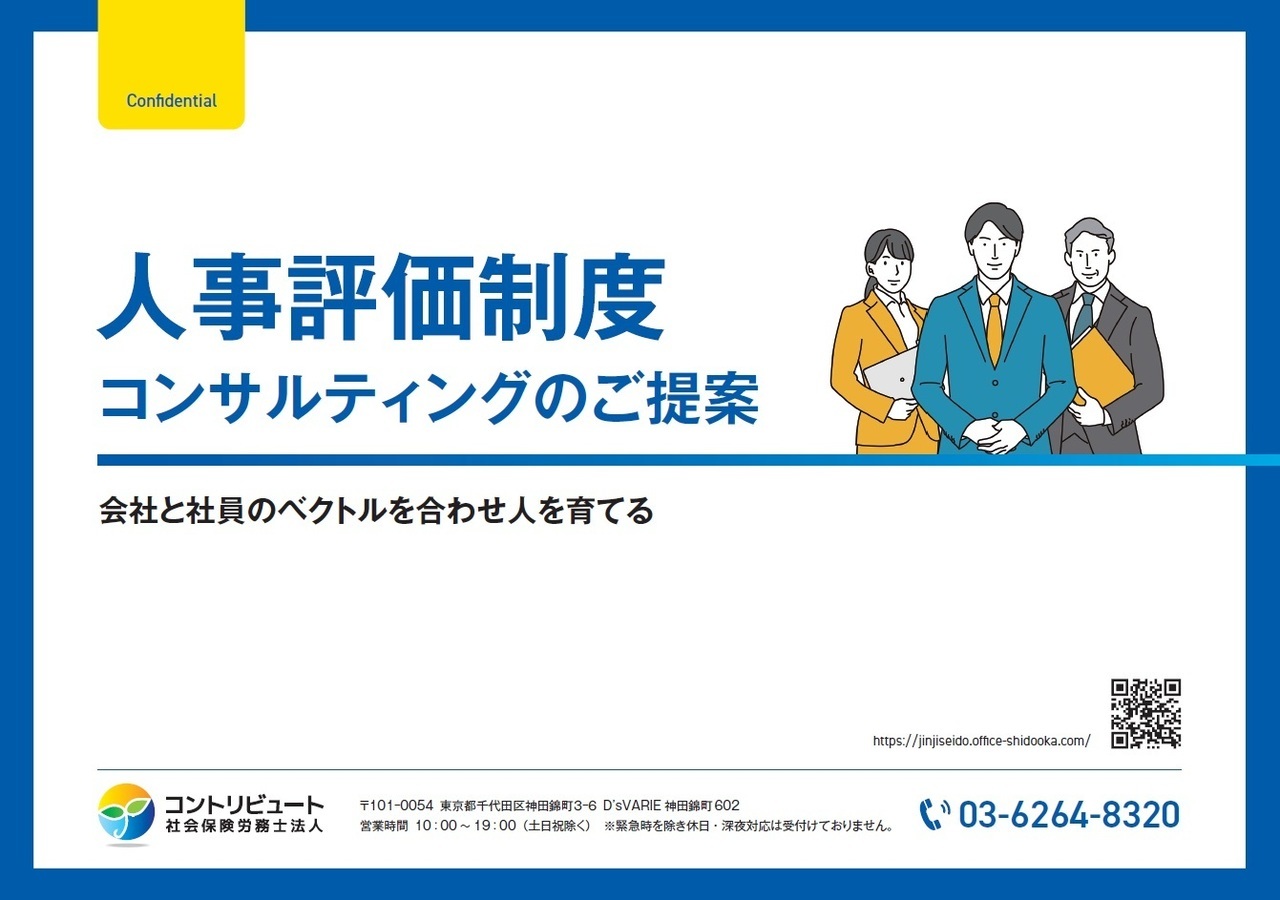〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-6 D'sVARIE神田錦町602
営業時間 | 10:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
人事評価制度の相談事例:部署ごとの評価基準設定のポイント
部署、職種による評価基準
相談者:会社経営者
弊社では、現在人事評価制度がなく、新規での導入を検討しています。そこで、導入するにあたり、評価基準を部署や職種ごとに、どこまで細かく設定した方がいいのか、わかりません。
部署、職種によってやっている仕事も全く異なりますが、この仕事の違いと評価基準の違いをどのように考えればいいでしょうか?
回答:社会保険労務士
部署や職種によって仕事が全くことなる場合に、全て同じ評価基準で運用することは無理があります。
どこまで部署ごとにするかはバランスと匙加減の部分となります。あまりに細かくわけ過ぎると、メンテナンスや管理に工数がかかることに繋がり、導入後に運用が難しくなります。
共通部分と部署ごとの評価基準をミックスさせるのが無難
人事評価制度の評価基準を設定する際、全社員に共通する部分と、部署ごとに特化した基準をミックスさせることが非常に有効です。
まず、共通部分として企業全体の価値観やビジョンに沿った評価項目を設定することで、全社員が一体感を持ち、企業目標に向かって一致団結することができます。
例えば、コミュニケーション能力やチームワーク、企業理念の理解度や実践などが共通部分の事例として挙げられます。
これらの素養、要素はどの部署にあっても、全社員にもっていて欲しい、大事にしてほしいとされる会社が大事にする企業文化に関わる部分とも言えます。
一方で、各部署の特性や業務内容に応じた評価基準を設定することも重要です。
営業部門では売上目標や顧客満足度、開発部門では技術力やプロジェクトの進捗状況、管理部門では人事、労務、経理といったそれぞれの分野の専門知識など、各部署の具体的な目標や業務内容に基づいた評価基準を設けることで、各社員の業務遂行能力や成果を適切に評価できます。
このように、共通部分と部署ごとの評価基準をミックスさせることで、評価の一貫性と公平性を保ちながら、各部署の独自性や専門性を反映した評価が可能となります。
さらに、全社員に共通する基準があることで、部署間の異動があった場合でも、社員は基本的な評価基準を理解しやすく、迅速に新しい役割に適応できるでしょう。
共通部分と部署ごとの評価基準をバランス良く取り入れることを、おすすめします。
部署ごとの評価基準、評価項目を作成する際の注意点
各部署ごとの評価基準や評価項目を設定する際は、部署ごとの業務内容や目標が異なることを考慮する必要があります。
各部署の特性に合わせた評価項目を設定することになりますが、部署間での評価基準の甘辛、レベル感をある程度合わせる必要がでてきます。
例えば、営業部門では売上目標の達成度、顧客満足度などが重要ですが、開発部門では技術力の向上やプロジェクトの進行状況が重視されるという結論がでたとします。
この場合に、営業部門と開発部門での評価基準のレベルを客観的にみて、妥当と考えられる妥当性と公平性のバランスをとる必要があります。
営業部門の評価基準が厳しすぎるのに、開発部門の評価基準はややぬるい。異なる評価基準になるため、単純比較はできませんがある程度のすり合わせは必要です。
また、評価基準を設定する際には、評価者による解釈の違いを避けるために、具体的で測定可能な項目を作成することが望ましいと言えます。
透明性を高めるために、評価基準や評価方法を全社員に明示し、納得感を持たせることも大切です。
評価基準設定のステップ
評価基準の設定ステップをみていきましょう。弊社では以下のような手順で設定・導入を進めていきます。
1. 社内の職種や部署の現状分析~区分の検討
まず、自社での社員の働く職種や部署などの現状を分析し、どのようなグルーピング、区分をすればベストかを検討します。
2. 等級制度のフレームを検討する
次に、等級制度のフレームを検討し、設計します。なお、この等級制度の設計と1の職種区分の検討は順番が逆でもさほど大きな違いはありません。検討しやすい方から検討する形でも構いません。等級制度については以下のページで詳細を検討しています。
3. 各等級・職種での評価要素(評価基準)の項目数を検討する
職種と等級の設計ができたら、評価要素の項目数を検討します。例えば、等級区分を5ランク、各等級で評価要素を5つ設定、職種区分を4種類とすると、5等級×5つの評価項目×4種類の評価要素=100項目のマスが全体の大枠として決まります。
4. 職種・部署が異なっても必要な共通部分を検討する
職種ごとに求められる評価要素よりも先に、職種や部署が異なっても自社の社員にとって必要な共通要素を「等級」ごとに検討します。これにより、部署がことなっても社員の階層ごとに会社が求める共通の要素(どのような社員に育って欲しいか)が徐々に明確になっていきます。
5. 職種・部署ごとの評価要素を検討する
最後に、職種や部署ごとに必要な評価要素を検討していきます。
(共通要素と職種ごとの評価要素)
共通要素と職種ごとの評価要素の割合をどのように割り振るかは悩みどころです。まとめ過ぎても評価がしにくくなりますし、一方で細かく分けすぎても制度が複雑になりすぎます。
評価項目の適正な個数について
評価項目の数は、過剰になりすぎないように注意が必要です。一般的には5項目程度、多くても7項目程度をお勧めしています。
あれもいれたい、この項目もいれない、となる気持ちもわかりますが、どうしても項目が多すぎると評価が複雑化し、評価者の負担が増すだけでなく、被評価者にとっても焦点がぼやけてしまいます。
これだけは絶対に譲れない!この評価項目があれば良いパフォーマンスをだせる土台になる、という重要な項目に絞り、各項目の評価が詳細に行えるようにすることが重要です。
評価項目を選定する際には、業務の重要な要素や成果に直結するポイントに重点を置きます。
なお、評価項目の選定と見直しは、継続的なプロセスと捉え、柔軟に対応することも求められます。
人事評価制度の導入や見直しでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
人事評価制度のお問い合わせはこちら
東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当法人では中小企業の人事評価制度作成、改定、運用のサポートを実施しております。
※ZOOMでのオンラインミーティングも対応可能です。
■東京都千代田区神田錦町3-6 D'sVARIE神田錦町602
■受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)